経歴
-
学生時代
帝京大学 外国語学部で英語を専攻。
大学4年時に、Faber Companyでインターンを始める。 -
2020
1年目 Faber Company新卒入社地方企業専門の営業チームに参画。
-
2022
2年目最年少でセールスチームのリーダーに。
-
2023
4年目セールスチームのマネージャーに。
-
2024~
5年目執行役員に就任。
入社5年目で最年少の執行役員に
執行役員として村尾さんが担う役割について教えてください。
一言で言うと「組織づくり」です。
正確には、エンジニアなどの専門職(エンジニアなど)を除いたセールスやカスタマーサクセス、採用や育成といった組織運営全般に携わっています。
私はCRO(Chief Revenue Officer=最高収益責任者)という役職に就いています。企業の利益には、顧客獲得から契約の継続・解約防止、営業活動のすべての要素が関わります。当然、それらを行う人材を確保することや、社員に長く活躍してもらうための環境整備やインセンティブ設計といった土台づくりも求められます。
結論、収益責任を果たすということは「組織づくり」に取り組むことと同義なのです。

20代にしてその重責を負うことになったと。入社後どのようなキャリアを重ねて執行役員へ就任したのですか?
地方企業様への営業からキャリアをスタートさせました。入社1年目は売上ゼロの月もあるほどのダメ営業でしたが、元上司が徹底的に寄り添ってくれたおかげで、徐々に成果を出せるようになったんです。
その後、日本全域の営業になり、入社2年目の終わり頃から史上最年少でセールスチームのリーダーを務めました。その後、2023年にセールスチームのマネージャーとなり、2024年に執行役員へ就任しています。こう話すと、一足飛びで昇進しているように見えますが、実際には階段を一つずつ上った結果、役員になったというのが私の感覚に近いです。Faber CompanyはG1・G1.5・G2・G3・役員といった形で役職のグレードが設けられています。私は入社1年目にG1、2年目にG1.5、3年目にG2、4年目の4月にG3とステップを踏み、5年目に役員となったんです。
楽な道のりじゃなく厳しい道の歩き方を淡々と続けてきた
一つずつ階段を上ったと言いますが、村尾さんはなぜその速度感で今のポジションに就くことができたのでしょうか?
与えられた環境で個人・組織の目標を達成した結果、自然と今のポジションになった。それ以外にはないのですが、私と他の社員との違いが何かというと、おそらく「基準値の高さ」にあるのかなと思います。私は他の人と比べて、仕事でもプライベートでも「大変だ」と思うラインの基準値が圧倒的に高いんです。もし「1日300件営業電話をかける」という行動目標を掲げたら、普通の人は1週間も続けたら心が折れてしまうでしょう。でも、私は淡々と続けられるしそれを大変だとも思いません。

それだけ行動を積み重ねられる背景には、どのような想いがあるのでしょうか?
楽な道のりを知りたいのではなく、厳しい道の歩き方を知りたいという想いが、私の行動の根底にある気がします。
人は「どうすれば最も効率的か」を考えます。それ自体は大切なことですが、楽な方法を探そうとするあまり、行動が止まってしまいがちです。私の場合は、ゴールに必要な行動がわかったらその道をただ歩くだけだと考えます。私はある意味、シャトルランで勝ってきたタイプなんです。シャトルランは競技特性上、「きつい」「苦しい」と感じた人から順番に脱落していきます。私は苦しいと感じるラインが非常に高いので、周りが離脱していっても走り続けられる。それを続けた結果、他のメンバーがついてこれない量を積み重ねて結果を出せたんです。「どうすれば効率的に営業成績を高められるか」といった、一般的な営業コンサルティングとは真逆の発想かもしれません(笑)。
その基準値の高さが村尾さんの“特異”なのですね。その感覚はいつから身についたのですか?
高校時代の経験は大きなきっかけになっていると思います。私は小学校から大学までサッカーに打ち込んでいて、高校時代の県大会で優勝し、全国大会に出場した経験が自分の成長につながりました。どんなにきつくても練習を続けたその日々が、圧倒的な行動を継続できる精神力を養ったと思います。頑張り続けた者だけが見られる景色をまた見たい。それが仕事のモチベーションになっていると思います。
今日より明日。目指すのは日本一継続力のある組織
リーダーシップを発揮するなかで意識していることは何ですか?
私が大切にしていることは、「メンバーと一緒に行動する」です。たとえば、スーツの出社が義務付けられているのなら私もスーツを着るし、もしみんなが朝8時に出社して営業するのなら私も8時に来る。セールスチームの在籍時は、私自身も最前線で商談しながらメンバーのマネジメントを行っていました。椅子にふんぞり返ってメンバーを叱責するのではなく、誰よりも高い基準で行動する姿を見せることで、メンバーに変化を促していきたいんです。
まさに「背中で語るリーダー」を体現しているのですね。
実際、私の姿に触発されて多くのメンバーが行動を変化させてきました。とはいえ、自分の当たり前が他のメンバーにとって当たり前ではないということは、常に意識しています。メンバーに求めるのは、「昨日より今日が良くなる」という小さなラインを超えること。その小さな積み重ねの連続が、結果として会社全体の成長につながると信じています。
その中で、私が心がけているのは「適切なゴール設定」です。多くの人が手を止めてしまう背景には、将来に対する漠然とした不安があります。情報があふれている昨今、どうしても他人と比較して不透明な将来に不安を覚えてしまいます。「自分は将来どうなるんだろう」「家族を養っていけるかな」と、種種雑多な悩みを抱えてしまう人は少なくありません。メンバーごとに適切なゴールを設定して、それに向けて何をすべきか一緒に考え伴走していく。そうやって、一つひとつの課題を解決しながら前進し続けられるサポートをしたいと思っています。

目指すのは「日本一相手のことを考え抜ける継続力のある組織」
Faber Companyの組織づくりにおいて、今後の目標は何ですか?
「昨日の自分の限界を今日超える」という行動を繰り返せる、「日本一継続力のある組織」をつくりたいです。営業の電話をするのであれば、昨日よりも1件多くかけてみる。それを20営業日続けられれば、1日1件の改善が大きな積み重ねになります。そうした継続力をメンバーには高めてほしいし、継続の意識がある人と一緒に働きたいと思っています。
それともう一つ、私が組織づくりをするなかで重視している素質があります。それは「相手のことを考え抜くこと」です。部門も役職も関係なく、Faber Companyで働く人全員にこの意識を持っていてほしいと思っています。たとえば、営業部門がお客様から「SEOで困っている」と相談されたのに何も答えられないなんてことがあったら大問題ですよね。相手のことを考えていません。お客様の問題に寄り添えず、明確なアイディアを提案できないのに、KPI達成のために商談を設定する。極端な話、これは詐欺に近いと思います。
同様に、たとえば人事部門の採用面接ではテンプレートに沿った進行をするのではなく、相手の心境やオンライン環境を想像し柔軟に対応できる能力が求められます。AIが多くの仕事を代替する時代において、人に残される仕事は「人の感情に寄り添うこと」です。だからこそ、瞬時に相手の立場に立って考えることは、あらゆる部門で結果を出すために必要なスキルであり、これこそがFaber Companyに求める人材像だと言えるでしょう。
相手を思いやることの大切さに気づいたきっかけは何ですか?
高校時代です。実は私、サッカー部から一度逃げ出したことがあるんです。コーチと大喧嘩して、そのままグラウンドを後にして山梨の寮から東京の実家に帰ってしまいました。翌日、父親に寮に送り戻されたんですが、そこで別のコーチに言われたことがあります。「お前もう、自分のために頑張るのは限界だろう?それなら、誰かのために頑張れよ。親父さん、仕事があるのにわざわざお前をここまで連れてきてくれたんだろう。自分の夢を応援してくれる親がいるのに、その人のために頑張れないのか?」核心をつかれたこの言葉を、今も忘れられません。この日以来、私は自分のために頑張ることをやめて誰かのために頑張ることに決めました。
もしも私が「最年少で執行役員になりたい」という気持ちだけで働いていたら、とっくに挫折していたでしょう。今もこうして働き続けていられるのは、私についてきてくれるメンバーや私を頼ってくださるお客様のためと言っても過言ではありません。その結果、私自身の当たり前の基準値は自然と上がっていきました。この考えに共感できる人と、Faber Companyを盛り上げていきたい。そして、会社で共に働く仲間とも「見たことがない景色」を一緒に見たいです。

※写真はすべてWeWork神谷町トラストタワーにて撮影
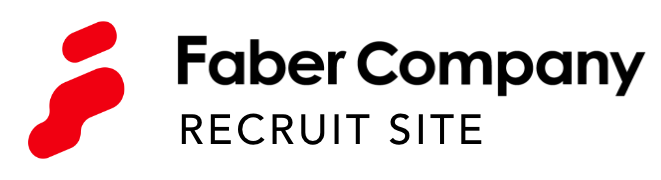
 TOP
TOP

