経歴
-
2001
人材アウトソーシング企業に入社 -
2004
個人事業主としてインターネットメディア事業を開始 -
2005
インターネットメディア事業を法人化 -
2012〜
Faber Companyに入社執行役員、プロフェッショナル事業部の責任者として従事。
成長を求め、自ら負荷をかけたキャリアチェンジ
Faber Companyには中途で入社されたのですよね。
2012年頃なので、もう10年以上前ですね。Faber Companyに入る前は自分で小さな会社を経営していました。経営者といっても、フリーランスとしてアフィリエイトサイトをいくつも立ち上げ・運営していて、成り行きで法人化したという感じです。業務委託やアルバイト、インターン生と仕事をしている、小さな規模の事業主でした。
会社経営を経て、Faber Companyへ入社したきっかけは何だったのでしょうか?
理由はシンプルで、今の働き方に限界を感じたというのがあります。一人ないしは小規模で働く生き方は、自由度の高さという魅力があります。嫌な仕事は断りやすいですしね。一方で、このままの働き方を続けても人生に広がりは生まれないと感じるようになりました。自分にもっと負荷をかけたいという想いが芽生えてきたんです。
筋トレに例えると分かりやすいかもしれません。一人でトレーニングをしていても、なかなか限界まで重いものを持ち上げようとはしない。でも、トレーナーがいる環境ではより高い負荷に挑戦しようという気持ちが生まれやすくなります。そういう環境に身を置くことで、一人では避けがちな挑戦に飛び込むようになり、結果的に成長できるのではないかと考えたんです。
そのタイミングで、昔から付き合いのあった代表の古澤暢央と話す機会がありました。彼に「よかったらおいでよ」と声をかけてもらったのが、Faber Company入社の直接のきっかけとなったわけです。

手仕事から生まれるコンテンツ。一次情報へのこだわり
現在の仕事内容について教えてください。
執行役員であり、プロフェッショナル事業部のコンテンツチームをリードしています。プロフェッショナル事業部には4つのチームがあるのですが、コンテンツチームはお客様のオウンドメディアをご支援し、コンテンツを制作・納品するのが主な役割です。
チームの役割は、もちろん与えられた数字目標を達成するというのが第一です。それに加えて、私たちの仕事から得られた知見を、ミエルカなどのソフトウェア開発に活かしていくという社内的な役割を担っています。コンテンツチームは「手仕事」によるコンテンツ制作を中心としてサービスを提供しています。そこで得た実践的な知識やノウハウを開発チームにフィードバックし、次のプロダクト機能に落とし込んでいくのです。
プロダクトをアップデートするために重要な役割を担っているのですね。コンテンツを作る上で、大事にしていることは何ですか?
「一次情報」を大事にするという点です。アフィリエイターとして活動していた頃から、紹介するサービスはできるだけ自分で購入して、実際に使ってみることを心がけていました。自分で体験できるのが最良ですが、大規模システム開発や不動産、専門的な会計ソフトなど、実際に導入することが難しいサービスもあります。その場合、お客様から直接、事例や詳細な情報といった「生な情報」を得ることを大切にしていますね。
特に自分でも購入可能な製品・サービスは、お客様から商品を提供いただくのではなく、自分で買って試すようにしているんです。なぜかというと、自分でお金を払って購入するというプロセスを経験したいから。
インターネットで買うのか、店舗で買うのか。店舗で商品を見た時に、「この金額だとちょっと高いな」と感じ、類似商品に目移りしてしまうのか。購買に至るまでの葛藤やリアルな感情はコンテンツに深みを与えます。
「仕事だからこの商品を推すけれど、そうでなければ正直、安い方を選んでしまうかもしれない」。こうした生々しい体験に基づく感覚の有無が、読者に伝わる・伝わらないの差を生むと思うんです。
入社前に抱いていた「負荷を感じたい」という欲求は、Faber Companyで実現できていますか?
はい。BtoBのお客様をはじめ、個人の仕事では支援したことのないプロジェクトに関われています。当初の狙い通り、負荷のかかる挑戦ができていますね。その中で成長・変化したのは、「自分がベストだと思っていることが、必ずしもお客様にとってベストではないこと」を学んだことだと思います。
お客様がコンテンツに求める要素は、人によってさまざまです。こちらがよかれと思い全力で提案しても、実はまったく異なる部分にお客様のニーズが眠っていたというケースはよくあります。これは、自分でサイトを運営していた時代にはなかった視点です。

ハードな仕事で求められるのは、苦労を許容できる適当さ
山田さんから見た、Faber Companyの魅力は何ですか?
「性格の良い人が多い」ことじゃないかなと思います。仕事を進める中で、人の手柄を自分のものにしようという、ずる賢いタイプの人はいないです。「これは私の力ではなく、〇〇さんの功績です」という言葉がすっと言えるメンバーが多いと思います。メンバー同士の仲も良くて、休日も一緒に遊んだりどこかへ出かけたりしているのをよく聞きます(笑)。だからなのか、組織全体で連帯感が強いとも感じます。成果そのものにコミットするのはもちろん、「チームのために頑張ろう」という意識が高いですよね。他者への貢献意識が強い気がします。
チームとしての連帯感に惹かれる人は、この会社に向いている人と言えますね。
そうですね。あと誤解を招く言葉かもしれませんが、この会社で成長したいなら「適当さ」も大事な要素だと思います。これはいい加減という意味ではなく、「許容できる人」という意味合いが強いです。Faber Companyは高いレベルの仕事が求められるので、正直、ストレスを覚えやすい環境だと思います。目標達成へのプレッシャーもあるし、仕事量も多い。だからこそ、あまりにきっちりやろうとすると、思い詰めてしまう気がします。目標に向かって努力することは大前提です。でも、どうしてもコントロールできないこと、思い通りにいかないことはあります。そうした現実に直面した時、「仕方ない」とある程度割り切れる適当さが、精神的な余裕を保つ上で大事です。
私は単発ですごい成果を出すよりも、アップダウンはありながらも長期的に見て伸びているという状態の方が価値があると考えています。そのためには、「続ける」ことが何より重要であり、続けていくためにはある程度の「適当さ」が必要不可欠ではないかと思うんです。
コンテンツの次はAI?プロを育む「無努力主義」
プロフェッショナル事業部にいる山田さんにとって、「プロ」とはどのような存在だと思いますか?
うーん……難しい。正直、私自身が自分のことをプロだと言うのは、ちょっとおこがましいとすら考えていますから。ただ、私が好きな経営学者の楠木建先生がおっしゃっている「無努力主義」という考え方には、すごく共感します。
これは先生自身のエピソードらしいんですが、先生は書いたり考えたりすることが大好きで、朝9時から書き始めて、気づいたら夜の11時になっていたことがあるそうです。周りから見ればものすごい努力をしているように見えるけれど、本人にとっては夢中になっているだけで、努力している感覚はない。この状態が理想であり、プロフェッショナルに近い姿なのではないかと思います。これだけ没頭できるものを、すぐに見つけられるわけではないでしょう。いろいろなことをやり込んでみることで、自分が夢中になれるものを掘り当てられるのかなと思います。
山田さんにとって夢中になれることが、まさにコンテンツ制作だったと。
そうですね。でも最近、長年この仕事を続けたことでちょっと飽きている自分もいるんです(笑)。今、私が興味があるのはAIの世界です。AIを活用すれば、それまで大企業しか扱えなかったようなデータ活用が、個人レベルでも可能になります。ある講演で登壇者が、「AIは人類が紙とペンを手に入れた時と同じくらいのインパクトがある」と言っていたことが、とても印象的でした。暇さえあれば、AIのことばかり考えている自分がいます。これからAIが社会をどう変えていくのか、その変化の渦中に身を置いてみたいという気持ちは強いです。この感覚が、新しい無努力主義の源泉だと思います。この気持ちに乗った先で、自分がどんな仕事に携わっているのか楽しみです。

※写真はすべてWeWork神谷町トラストタワーにて撮影
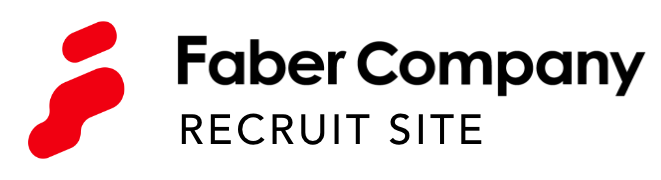
 TOP
TOP

